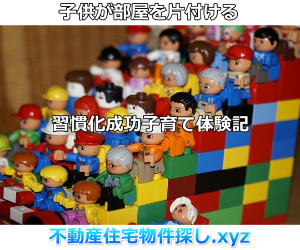
- 子どもが部屋を片付けない!
- なぜか親が片付けている!
- おもちゃの片付けをしない!
子供部屋を用意したいと思っても、今の我が子を見ているとこの先が心配。
いずれまた親がすべてを片付けるような状況になるのなら、いっそ部屋なんていらないのでは?
実家にいった時でも親がおもちゃもお菓子も食事の片付けも済ませるような環境になっているケースも多い。
そんな親御様に子どもが部屋の片付けをするようになった我が家の方法をご紹介しています。
子供が部屋を片付けない過去の歴史

我が家でも上の子が2歳、3歳、4歳の頃にはかなり怒られていました。
子育てをする時に叱責をしないようにしたい。
でもいつも何か言い訳をしてやらない理由を並べる子供には甘い顔を見せません。
おもちゃも片付けない

リビングでもダイニングでも和室でも寝室でもどこでも部屋中に遊んだものを放置。
これが3歳、4歳の頃の子どもたちでした。
しかし、この状況に子どもだからと甘んじてしまう時期もあります。
通用しない無駄な策

この時、以下のようなアイデアを使っても全く変わらないことが多いのです。
- 専用のボックスを用意
- キャラクターなどのシールを貼って気を引く。
- 名前を書いて片付けをさせる。
このような方法を自分たちもやってみましたがことごとく無駄に終わりました。
子供が部屋を片付けた教育方法

いくら言っても無理!
結局は子供が寝てから親が片付ける。
中学生、高校生になってもいつまでも親が管理しないと物が散乱している。
こんな状況にしたくないと思ったら、まず何をすればよいのか?
今出ているものはゴミ!

我が家が活用したのが、ごみの日です。
「ごみの日の朝にそのまま床に落ちているモノは全て捨ててよいということ!」
これがルールということにしました。
- ゴミではない
- 捨てられたら困る!
こう思うものは全て何かのケースに入れたり、おもちゃ箱に片づけるなどをしないと問答無用で全てゴミ袋で回収します。
(もちろん本当に捨てるかどうかは判断をしますよ)
でも実際に捨てる様子を見せるためにも、屋外に専用のごみ箱を用意。
そして、実際に捨ててしまう様子まで見せました。
意識改革は危機感から

幼稚園や小学校、中学校、高校まで自宅から通勤をする間は忘れ物やモノを失くすのを防ぎたい。
問題はこの時にすべて親がカバーしてしまうかどうかです。
「なくなったら買わない。」
子供は賢い。
自分に何かあったら全て親が最後には何とかしてくれる。
こんな気持ちにさせてしまうと、いつまでも自分でやろうとしません。
でも親も子供も関係ない。
自分の事は自分でやる。
この管理意識を持たせることで、放置はできなくなります。
お出かけ前には整理整頓

特に我が家が大事にしているのは、外出をする前の時間。
- 身支度をさせる
- トイレを済ませる
幼稚園児の時からこの2つは徹底しているパパママも多いはず。
でも我が家は、掃除を全て済ませてからというのがプラスされます。
家に帰ってきた時、以下の内容は完了した状態を求める。
- すぐに夕飯が食べられる(炊飯器もセットする)
- お風呂も掃除を終えて給湯を予約済
- ダイニング、リビング共に何も床にモノがない状態
- 次の日が学校なら、翌日の支度も完成させる
上記は完全に終わらせてからでなければ、お出かけはしません。
支度を完全に終わらせるからお出かけができる。
こういう意識が一度定着すると、子供が自発的に自分のやるべきことを早期に終わらせるようになりました。
「どこかに行きたいと言うなら、全て終わらせてから。」
このルールを作ると、意外と家の中はいつもきれいになっていると思いますよ。